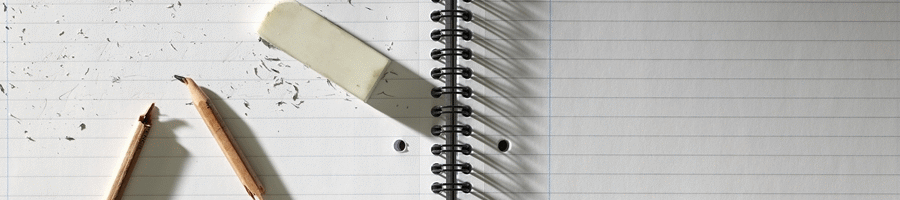職務著作について
(本稿は、知財管理59巻1月号(2009年)97頁~101頁に掲載されたものです。) 弁理士 宮澤 岳志
抄録
著作物を実際に創作することができるのは自然人であるが、わが国著作権法では一定の要件を満たす著作物に関し、会社、国、地方公共団体、学校などの法人等が著作者の地位を得ることができる職務著作(法人著作)の制度がある。
本稿では、職務著作の制度に関し要件、効果等を平易に説明するとともに、簡単な例題を用いて職務著作の成否について検討し、最後に職務著作について実務上注意すべき点について説明する。
目次
1 はじめに
2 職務著作の制度概要
3 職務著作の成立要件
4 職務著作の適用の効果
5 職務著作の適否についての検討
6 実務上の留意点について
7 おわりに
1 はじめに
会社の従業員が得意先向けに提案書を作成したり、社内会議や閲覧用に報告書やレポートを作成したりすることは日常の業務として普通に行われていることかと思います。提案書や報告書などは思想または感情を創作的に表現したものでありますから、多くは著作権法上の著作物(第2条第1項第1号)に該当いたします。会社内で作成される著作物には、提案書や報告書の他にも例えば写真、絵画、音楽、又はプログラムなど様々なものが挙げられるでしょう。
著作物を実際に創作することができるのは人間(法律上の「自然人」)であることは疑いのないところですが、わが国では一定の要件を満たす著作物に関し、会社、国、地方公共団体、学校など(これらを「法人等」といいます)が「著作者」の地位を得ることができる制度が設けられています。この制度を、職務著作(法人著作)の制度といいます。
本稿では、職務著作の制度に関し要件、効果等について平易に説明するとともに、ごく簡単な例題を設定した上で職務著作の適否について検討します。最後に職務著作について実務上注意すべき点について説明いたしたいと思います。
2 職務著作の制度概要
(1)著作権法第15条
職務著作の制度は、著作権法第15条に定められています。まず始めに条文を確認しましょう。著作権法第15条第1項は次のように定められています。
「法人その他使用者(以下「法人等」)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」
この条項は、主として5つの要件で構成され、あわせて要件を満たした場合の効果も示されています。これらの詳細は後述することといたします。
(2)制度の意義
職務著作の制度とは、従業員により職務上作成された著作物について法人等に「著作者」の地位を与えようとする制度です。
ここで注意すべきは、この制度が法人等に著作権等が帰属する旨を直接的に定めているのではなく、法人等に著作者の地位を与える旨を定めていることです。
著作権法において「著作者」の地位を得ることは極めて重要な意味があります。なぜならば、著作者は「著作権」並びに「著作者人格権」を享有する旨が定められているからです(17条1項)。ある著作物について職務著作が適用されるとその著作者が法人等になりますから、結果として法人等に「著作権」並びに「著作者人格権」が帰属することになります。
ところで、特許法では「職務発明」に関する規定がありますが、著作権法における職務著作の制度とは規定する内容が著しく異なります。すなわち、特許法では発明者が「特許を受ける権利」を原始的に取得する点に関し例外は一切ありません。職務発明についてもまずは発明者に特許を受ける権利が原始的に帰属し、特許を受ける権利を法人等に移転する場合には契約等による取り決めが必要です(特許法第29条、第35条)。実用新案法や意匠法においても同様です。職務発明では、法人等に権利を移転するに際して「相当の対価」に関する取り決めが必要になるのが一般的です。これに対し、職務著作の場合は法人等に著作権等が原始的に帰属するため、相当の対価などのデリケートな問題は生じないことになります。
それでは、職務著作の制度はなぜ設けられたのでしょうか。主な理由として次の2点が挙げられるでしょう。1点目は、職務上作成される著作物はその作成に伴うコストを負担したり、その創作に係るリスクを負担したりするのは法人等であるという理由です。コストやリスクを負担する立場に鑑みれば、著作者を法人等とすることが合理的であると考えることができるでしょう。2点目は、法人等で作成される著作物の著作者を法人等とすることを制度上の原則にすれば、日々大量に発生する著作物について、わざわざ個々に権利の所在確認をする必要が無くなりますので、著作物の円滑な利用という点において便宜的であり、且つ、より安定的な秩序を形成し得るという理由です。会社内では著作物が次々に生みだされていますから、会社内で発生する著作物の特質を考慮して、権利者を法人にすることで管理をシンプルに一元化したものであると言えるでしょう。
3 職務著作の成立要件
職務著作の成立要件を整理したいと思います。職務著作に関する著作権法第15条第1項には5つの要件が定められています。なお、第2項はプログラムの著作物に関して別個独立して定められたもので、第1項に定める要件の1つを欠く点を除き、同一の内容となっています。
(1)職務著作の5要件
① 著作物が法人等の発意に基づいて作られたものであること。
第一の要件は、著作物が法人等の発意に基づいて作成されたものであることです。著作物の作成の意志が直接又は間接に使用者の判断にかかっているような場合、換言すれば、使用者である法人等が著作物の作成についてイニシアチブをもっているような場合であれば、この要件に該当いたします。
② 法人等の業務に従事する者が作成したものであること。
第二の要件は、法人等の業務に従事する者が作成した著作物であることです。一般的にはいわゆる雇用関係にある従業員や、会社役員などが該当いたします。なお、派遣労働者については、派遣先から指揮命令を受ける点を考慮してこの要件に該当すると考えるのが多数説です。一方、アルバイトによる労働者はこの要件に該当しないと考えるのが一般的な見解です。
③ 従業者が職務上作成した著作物であること。
第三の要件は、従業者が職務上作成した著作物であることです。従業者が職務上作成する、すなわち、従業者が自分に与えられた仕事として著作物を作成すれば、職務上作成した著作物に該当いたします。例えば、自宅で作成したものであっても職務に基づいているものであれば、職務上作成に該当するといえるでしょう。
④ 法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物であること。
第四の要件は、法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物であることです。単に、発行者名義が法人等であるだけではこの要件を満たしません。すなわち、その著作物の著作者としての表示に、法人等の名称が表示されている必要があります。表示例としては、著作物の表紙、裏面、その他奥付などに、「著者:○○株式会社」とか、「制作著作:○○株式会社」というものであれば明確にこの要件を満たすでしょう。また、本質的な意味は異なるのですが、近年では多く利用されている©マークを活用して、「©2008○○株式会社」と表示しても、著作者表示としての役割を果たすものと思われます。
(なお、©の本来の意味は、アメリカにおいて「著作権者」を示すために用いられるマークです。)
また、条文上「公表するもの」と規定されていますが、これは使用者の著作の名義で実際に公表したものだけではなく、使用者の著作の名義で公表することを予定している著作物も該当することを意味しています。
⑤ 著作物の作成時における契約等において別段の定めがないこと。
第五の要件は、著作物の作成時における契約、勤務規則その他において、従業員を著作者とする等の別段の定めが存在しないことです。
法人等と従業員との間で著作者に関する契約等がなされていれば、その契約等で形成された当事者の意思を尊重して判断することになります。
(2)その他
プログラムの著作物に関しては、第15条第2項に規定があり、同条第1項の「法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物であること」の要件がありません。
公表に関する要件が無いのは、プログラムの著作物は公表を前提としないで開発されるものもあれば、具体的に法人等の名義が示されないものもあるので、これらの特殊な事情などを考慮したためです。
4 職務著作の適用の効果
著作権法第15条の各要件を満たすと、その著作物について法人等が「著作者」の地位を取得いたします。そして、法人等が著作者の地位を得た結果、法人等が著作権及び著作者人格権を享有することになります(第17条1項)。
ここで、公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、及び、同一性保持権(第20条)により構成される著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません(第59条)。したがって、職務著作が適用されると著作物の人格的な側面を保護する著作者人格権も法人等の一身に専属することになり、当該法人から移転することができません。
なお、複製権等(第21条~第28条)の著作権は移転可能な財産権でありますので他人に譲渡することが可能です(第61条)。
5 職務著作の適否についての検討
ここでは、職務著作についての理解を深めるため、例題を用いて職務著作が成立するか否かについて検討したいと思います。
(1)例題
会社Xの営業部長Aは、部下である営業マンBに対し、取引先であるY社向けに自社商品の提案書Pを作成するように指示をした。
営業マンBは、取引先であるY社から受注できるよう、デザイン等に創意工夫を凝らした斬新な提案書Pを完成させた。提案書Pの表紙や裏面には著作の名義として会社Xの表示がされているが、営業マンBの名前は一切表示されていない。
会社Xと営業マンBとの間には、自己が作成した著作物の取扱いに関し、勤務規則等にて別段の取り決めをしていない。今回の提案書Pに関しても同様である。
さて、提案書Pの著作者は誰か。
(2)検討
前記例題について、職務著作の適否について検討したいと思います。(あくまで例題ですから深く考えず、シンプルに検討しましょう。)
① 「法人等の発意」について
会社Xの営業部長Aから指示を受け、部下である営業マンBがY社向けの提案書Pを作成しておりますので、提案書P(著作物)の作成に関し、第一の要件である「法人(X社)の発意に基づく」という要件は満たしているといえるでしょう。
② 「法人等の業務に従事する者」について
提案書Pを作成した営業マンBは、事例から会社Xに雇用されていると考えてよいでしょう。したがって、営業マンBは、「法人等の業務に従事する者」であるといえます。
③ 「従業者が職務上作成した著作物」について
営業マンBは、取引先であるY社から受注できるように提案書Pを作成しましたので、自分に与えられた仕事として提案書Pを作成しています。したがって、「職務上作成」に該当するといえます。
④ 「法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物」について
提案書Pの表紙や裏面には著作の名義として会社Xの表示がされているとありますので、法人等(会社X)が自己の著作の名義の下に公表する著作物であるという要件を満たします。
⑤ 「著作物の作成時における契約等において別段の定めがない」
例題では、会社Xと営業マンBとの間には、著作物の取り扱いについて勤務規則等にて別段の取り決めをしていないことがわかりますので、この要件を満たします。
(3)結論(検討の結果)
この例題では、著作物である提案書Pについて職務著作の規定(第15条第1項)が適用され、提案書Pの著作者はX社となります。
この結果、提案書Pについての著作権及び著作者人格権は、X社に帰属することになります。
6 実務上の留意点
これまでの説明で、職務著作の制度の概要が理解できたかと思います。職務著作の制度は、会社や学校などが著作者の地位を獲得できてしまうダイナミックな制度だと言えるのではないでしょうか。
著作物について職務著作が適用されるか否かは、当事者(著作物に関係する法人並びに自然人)に極めて重大な影響を与えるものです。裁判例では、事後的に著作者が誰か(ひいては著作権等の帰属は誰か)について争われた事件が多く存在します。
実務上は著作権法における職務著作の制度を十分に把握することが重要です。職務著作の要件に該当するか否かについて疑義がある場合や、著作物の性質上明確に権利の帰属を確認すべきものについては、積極的に当事者の意思確認を行うことが重要でしょう。
一方、職務著作の要件を満たさない限り、法人等が著作者となることはありません。著作権等の帰属が誰にあるかについて、職務著作の適否に配慮しつつ確認することも大切でしょう。
7 おわりに
以上、職務著作について簡単に説明をいたしました。著作権法の中でも例外的な制度ですので、制度の理解は実務上大変有益であると思います。社内ルールの確認又は策定の契機になれば幸いです。
参考文献
1) 加戸守行『著作権法逐条講義〔五訂新版〕』(著作権財産センター、2006年)
2) 斉藤博『著作権法〔第2版〕』(有斐閣、2004年)
3) 中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)
4) 作花文雄『詳解 著作権法〔第2版〕』(ぎょうせい、2002年)
5) 田村善之『著作権法概説〔第2版〕』(有斐閣、2001年)
6) 半田正夫『著作権法概説〔第11版〕』(法学書院、2004年)